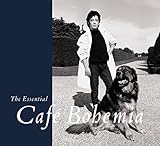決してヒット・チャートには馴染みそうもない、荒削りでありながら、しかし理性的に制御されたパッションを内包したそのサウンドは、80年代チャートの中心を担っていた歌謡曲と比較して、明快でもポップでもなかったのだけど、前作『No Damage』の余波も手伝って、オリコン年間チャート22位の好セールスを記録した。
当時の日本において、ヒップホップというジャンル自体がほぼアンダーグラウンドな存在だったにもかかわらず、それを大々的に取り入れて、しかも商業的にもキッチリ結果を出したのだから、同業者としては強いリスペクトと共に、危機感も大きかったんじゃないかと思う。
当時の日本において、ヒップホップというジャンル自体がほぼアンダーグラウンドな存在だったにもかかわらず、それを大々的に取り入れて、しかも商業的にもキッチリ結果を出したのだから、同業者としては強いリスペクトと共に、危機感も大きかったんじゃないかと思う。
このアルバムがリリースされた1986年前後というのは、元春に限らず、日本のメジャー・シーンにいるアーティストにとって、様々な形はあれど、大きな転機を迎えることが多かった。商業的に肥大化したサザンを一旦休養した桑田佳祐は、原点に立ち返るべくKuwata Bandを結成、ストレートなロックン・ロールを追求することによって、サザン以外の可能性を模索していたし、日本人離れしたファンクネスとずば抜けた歌唱力を持って一躍シーンに躍り出た山下達郎は、これまでの必勝パターンとは真逆のベクトル、内省的な歌詞と箱庭的に作り込んだデジタル・サウンドとの融合に苦悶し、長い袋小路の岐路に佇んでいた。
「歌謡ロック」と揶揄されることも多かったBOOWYは、コンポーザー布袋のビジョンである、ニュー・ウェイヴ以降のUKアバンギャルドと、一見ドライながらドメスティックな共感を得る歌詞とのハイブリットなサウンド、その完成度の高まりと共に行き詰まり感がメンバー全体に蔓延し、その短いキャリアに自ら潔い終止符を打とうとしていた。
「歌謡ロック」と揶揄されることも多かったBOOWYは、コンポーザー布袋のビジョンである、ニュー・ウェイヴ以降のUKアバンギャルドと、一見ドライながらドメスティックな共感を得る歌詞とのハイブリットなサウンド、その完成度の高まりと共に行き詰まり感がメンバー全体に蔓延し、その短いキャリアに自ら潔い終止符を打とうとしていた。
これまで築き上げてきたキャリアに対して、少しでも真摯なスタンスのアーティストなら、作品クオリティの維持と商業的成功との両立を成し遂げている元春の一挙一動は、注目に値するものだったと思われる。
それだけ内外に影響を与えた『Visitors』だったけど、元春自身はそこから更にヒップホップを掘り下げることはしなかった。
ここ日本において本格的にヒップホップを根づかせるためには、ワン・ショットのインパクトではなく、言い方は悪いけど、二番煎じか三番煎じまで畳みかけていかないと、定着しないはずである。なのに元春、『Visitors 2』的なアルバムを作らなかったのは、もちろん戦略的な面もあるだろうけど、常に進歩することを求められるトップ・アーティストとして、ひとつの色に染まらない、特定のカテゴリに収まりたくない、ある種の反抗心のようなもの、それと使命感もあったのだろう。
時たま出演するバラエティやインタビューでの発言でも知られるように、基本マジメな人である。ただ、大多数の人より価値基準や行動規範がちょっとズレているだけで、空気を読まず我が道を行く思考回路については、あまり突っ込んじゃいけないところ。一歩間違えれば社会的に孤立してしまいそうなところを、基本ピュアネスにあふれている元春、本人としてはそれがごく普通の事柄であり、何事においても誠実に答えているだけなのだから。
当時の元春が目指していたのは、洋楽の安易な移植ではないロックを日本に根付かせること、そして、いまだ現時点においても知名度の高いナンバー”Someday”に凝縮されているように、基本ポジティブなメッセージを伝えるため、ロック・ミュージックという手段を使っていた。そりゃ中にはネガティヴなテーマの曲もあるけど、基本はその人柄から窺えるように、真摯でピュアなメッセージである。
シリアスでリアルなメッセージを伝えるのに、当時のストリート・カルチャーに深く根付いていたヒップホップというサウンドは有効だったけど、サウンドというツールは、あくまで伝達の手段である。そこにこだわりを持つことは決して悪いことではないけど、そこへの執着が強すぎると、本来伝えるべきメッセージがボヤけてしまう。器ばかり磨き上げてもダメなのだ。
『Visitors』で糸口を掴んだばかりのヒップホップ・サウンドも、そこを一点集中で突き詰めるのではなく、これまで学び得たノウハウの一つとして、更に貪欲な吸収を行ない、そしてそれらをミックスし練り上げこねくり回した結果として、この『Cafe Bohemia』がある。
お茶の間レベルで理解できるレベルにまで噛み砕いたアバンギャルド・サウンドとロック的イディオムとの融合を見事結晶化させた『Visitors』に対し、今回の『Cafe Bohemia』、表面上はワールドワイドでジャンルレスな音楽の追求、スタイリッシュなジャケット・デザインから窺えるように、その気だるい居ずまいから、以前のポップ性を擁したロックン・ローラーの姿は想像できない。Style CouncilやStingからインスパイアされた、ジャジーなinterludeは、ロック的衝動やダイナミズムからは最も遠いところで鳴っている。
ただ同時に、表面的にはロック的サウンドから遠ざかりながらも、ロックの構成要素であるパッションは減じず、抽出されたメッセージ性に最もこだわっていたのは、日本においては元春が第一人者であったことは誰も否定できない。
ロック的イズムへのこだわりが強くなるあまり、敢えてサウンドの比重を弱め、言葉そのものの持つ力を引き出したのが、この頃から始まるスポークン・ワード(ポエトリー・リーディング)である。もともとは1950年代のビート・ジェネレーション時代に端を発し、その代表的作家Jack KerouacやAllen Ginsbergらによる、ニューヨークのライブハウスでの詩の朗読パフォーマンスなのだけれど、不定期レギュラーとなっている教育テレビ『ザ・ソングライターズ』での1コーナーとして、目にした人も多いはず。
ロック的演出を一旦剥ぎ取り、言霊本来の力と朗読力のみによって繰り広げられる、言葉のぶつけ合いと受け合い。そこはステージという多人数:1という構図ではなく、見る人によってそれぞれ解釈が違い、結果、1:1という、至極パーソナルな関係性が築かれている。その真剣勝負は互いに極度な緊張状態を誘発し、結果、体力の減少が著しい。安易なジェスチャーやメロディでごまかそうとしない所に、彼の潔さがうかがい知れる。
1. Cafe Bohemia (Introduction)
2. 冒険者たち Wild Hearts
ちなみにこのアルバム、これまでの元春のアルバムはすべてソロ名義だったのに対し、ここから何枚かは”with Hertland”と併記されている。レコーディング、ライブ双方を精力的に行なっていた頃であり、バンドとしての一体感が、これまでとは明らかに違っている。
何というか、百人が百人とも、「これはロックだ」というサウンドではない。ヴォーカルは明らかに元春そのものなのだけれど、ホーン・セクションを前面に出したソウル・テイスト濃いサウンドは、日本人単独では出せなかったグルーヴ感がある。
でも、これが元春の目指すところの、ロックなのだ。
3. 夏草の誘い Season In The Sun
肩ひじ張ってない歌詞が、俺は好き。『Someday』以前に頻発していた、ちょっとスカしたシティ・ボーイのシニカルな呟きより、このようなストレートなメッセージを爽やかに歌えるようになった、この時代の元春のファンは今も多い。
そうさ これが君への想い 何も怖くはない
Just One More Weekend いつでも 君のために戦うよ
Smile Baby 汚れを知らない 小鳥のように
4. カフェ・ボヘミアのテーマ Cafe Bohemia
5. 奇妙な日々 Strange Days
このアルバムの中では比較的ストレートなロック。ちょっとエスニック入ったピアノなど、そこかしこで正しくストレンジな音が入ったりなどして、普通のサウンドでは済ませようとしない、チャレンジ・スピリットが強く出ている。
6. 月と専制君主 Sidewalk Talk
ちょっとアフリカン・ポリリズムのエッセンスが入った、ちょっと奇妙な質感の曲。後年、このタイトルでセルフ・カバー・アルバムをリリースするのだけど、何かしら思うところがあったのだろう。地味だけど、なんとなく記憶に残り、妙にクセになる曲である。これまでの、そしてこれ以降の元春にも見当たらない、不思議な浮遊感のある曲である。
後半のブギウギ・ピアノとホーン・セクションとの掛け合い、ルートを外れそうでいて、きちんと本筋は外さないベース・ラインなど、ほんとバンドの一体感が出ていて、レコーディングも楽しげだったことが想像できる。
7. ヤングブラッズ Youngbloods
1985年2月、国際青年年のテーマ曲としてシングル・リリース。年間チャートでも63位と健闘した。やっとまともにトップ10ヒットとして世間に認められたのが、この曲である。確かにNHKなんかでは頻繁に流れていたため、タイアップ効果も大きかったとは思うけど、でも、この曲にはそれを超えたパワーがみなぎっている。
直訳すれば「若い血潮」と、いきなりダサくなってしまうけど、それを恥ずかしげもなく堂々と歌えるのが、やはり元春である。そのポジティヴなパワーの前では、ちょっとした恥じらいなどは吹き飛んでしまう。
この頃の元春としては珍しく、カタカナ英語が頻発した歌詞なのだけれど、力強いバンド・サウンドがそのうすら寒ささえ吹き飛ばしてしまう。
元旦に撮影されたという、この有名なPV、ほんと何度見てもワクワク感が募る。
元旦に撮影されたという、この有名なPV、ほんと何度見てもワクワク感が募る。
冷たい夜にさよなら
その乾いた心 窓辺に横たえて
独りだけの夜にさよなら 木枯らしの時も 月に凍える時も
いつわりに沈むこの世界で 君だけを固く抱きしめていたい
8. 虹を追いかけて Chasing Rainbow
ちょっとDylanのフェイクっぽいヴォーカルが時たま気怠くイイ感じなのだけど、もしかしてただ単にキーが高いだけなのかもしれない。
9. インディビジュアリスト Individualists
暴力的なスカ・ビートに乗せた性急な元春のヴォーカルが、『Visitors』を彷彿とさせる。硬質な言葉を叩きつける元春は、すべてのリスナーへ向けてアジテーションを送っている。バンドのどの音も攻撃的である。ひたすら単調なビートを刻むリズム・セクション、変調したギター・カッティング、地底をうねるベース・ライン、どれも体制へのもがき、抵抗が見え隠れする。
10. 99ブルース 99Blues
呪術的なアフロ・ビートと、それを切り裂く重苦しいアルト・サックスの調べ。こちらも『Visitors』サウンドの上位互換であり、様々なサウンドとのハイブリットで構成されている。
この曲での元春はかなり饒舌。どこかトピカル・ソング風にも聴こえる、社会風刺も混ぜ込んではいるが、そこまでシリアスにならないのは、やはり根が性善説な人だからなのか。
いつも本当に欲しいものが
手に入れられない
あいかわらず今夜も
口ずさむのさ
99 Blues
11. Cafe Bohemia (Interlude)
12. 聖なる夜に口笛吹いて Christmas Time In Blue
クリスマス・ソングにレゲエ・ビートを組み合わせる発想は、これまでなかったはず。もしかして前例はあったかもしれないけど、ここまでスタンダードに残る歌になったのを、俺は知らない。それだけクオリティが高いのだ。
クリスマス・イヴのワクワク感とクリスマス当日の「もうすぐ終わっちゃう」感を淡々と、しかもわかりやすく描写したのが、この曲。歌謡曲全盛だった当時、しかも12インチ・シングルでのリリースだったにもかかわらず、そこそこのヒットを記録したのは、純粋に曲の良さと歌詞の良さ、そしてレゲエ・アレンジの勝利だろう。
愛している人も 愛されている人も
泣いている人も 笑っている君も
平和な街も 闘っている街も
メリー・メリー・クリスマス
Tonight's gonna be alright
13. Cafe Bohemia (Reprise)
で、俺にとっての元春というのはここくらいまで。この後の元春はアッパーな時期とダウナーな時期とが交互に訪れている。そのバイオリズムの振り幅が大きすぎて、ちょっと聴くのが辛くなってきたファンというのは、多分俺だけではないはず。
その後のホーボー・キング・バンドやコヨーテ・バンドとのルーツ・ロック的セッションも味わい深くて良いのだけれど、キャリアのピークを知ってしまっている俺としては、ちょっと物足りなさも感じてしまう。ただ、ここに至るまで経てきた元春の軌跡を鑑みると、もっと気合入れてよ、とも言いづらい。
困ったものである。
The Essential Cafe Bohemia
posted with amazlet at 16.02.07
Sony Music Direct(Japan)Inc. (2014-05-12)
売り上げランキング: 18,499
売り上げランキング: 18,499
EPIC YEARS THE SINGLES 1980-2004
posted with amazlet at 16.02.07
佐野元春
Sony Music Direct (2006-06-28)
売り上げランキング: 51,279
Sony Music Direct (2006-06-28)
売り上げランキング: 51,279