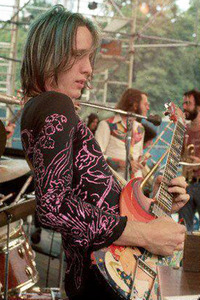ソロとバンド活動を並行して行なっていた70年代、大量のアイテムをリリースしてきたToddだけど、この年の純粋な新作は『Initiation』のみ。前年プロデュースしたGrand Funkが大ヒットして、オファーだってそこそこあったかと思われるけど、そういった形跡もない。表立ったスタジオ・ワークは、あんまりやってなかったようだ。
この時期のToddの活動は、スタジオ・ワークより、むしろライブの方に重点が置いている。レコード・デビューはしたけど、まだソロ・プロジェクトの色彩が濃かったUtopia が、メンバーの固定化によってコンセプトが決まり、徐々にバンドらしくなっていた頃と一致する。
その後、サウンド・メイキングの柱となるRoger Powellが加入したことで、Toddのワンマン・バンド色は薄くなってゆく。それは彼自身が望んだことでもあった。
なので、意思疎通やアンサンブル固めもあって、この年はライブ三昧。70年代のToddといえば、ずっとスタジオに引きこもってレコーディングばっかりやっていた印象が強いけど、その合間を縫って数多くのライブをこなしている。
オフィシャルでのリリースはなかったけど、デモ制作や後年発掘された『Disco Jets』など、当時は未発表に終わったプロジェクトも数多い。べアズヴィルのエンジニアとして、ちょっとしたスタジオ・ワークや、付き合いのあるアーティストからの依頼もちょくちょくあっただろうし。ソロでもバンドでもツアーをやっていたから、まとまった時間が必要なプロデュースまではできないけど、軽いフットワークで短期の仕事を請け負ったりしている。なんか派遣社員みたいだな。
ちょっと偏屈なところもあるけど、長年の経験に基づいた仕事の早さと要領の良さは、ベテランならではの得難いスキルである。まぁちょっと雑でアバウトなところはあるけど、納期と予算はきっちり守る。時に散漫になりがちなスタジオ・ワークにおいて、彼のような取りまとめ役は、引く手あまただった。
案外エゴを押しつけず、クライアントの意向に沿うToddの仕事ぶりは、おおむね好評だった。ジャンルや音楽性にこだわらず、長年の経験に基づく引き出しの多さから、全方位どのアーティストにも対応できる順応性。それでいて予算管理もしっかり行なうし、アーティストの意向を可能な限り受け止めつつ、実際のポテンシャルよりちょっと背伸びした程度のレベルに導いてしまう印象操作。こう書いちゃうと、なんかすごい人徳者みたいだな。
実際のところ、彼が手がけたプロデュース・ワークは多岐に及ぶ。Mitch RyderとXTCなんて、そりゃ両極端だもの。それでいて、もちろん全部が全部じゃないけど時々デカいヒットを飛ばしちゃうんだから、評判はさらに高くなる。成果を出すほど、あらゆる方面からさらにオファーが舞い込む。アーティストとしてはイマイチだけど、プロデュース業はずっと緩やかな右肩上がりだった。
でも時々、「ちょっと場違いじゃね?」って案件も、軽く引き受けちゃったりするのが、この人のお茶目なところ。Beatlesへの長年のリスペクトが実った、Ringo Starr のオールスター・バンド参加はわかるとして、フロントマンRic Ocasekの代わりにNew Cars加入っていうのは、ちょっと節操なさ過ぎ。まぁTodd以外、引き受け手がなかったんだろうな。
去年だって、なぜかYesと一緒に全米ツアーを回ってたりするし、一体どこに接点があったのか、一般人にはなんとも不明。多分、我々には知る由もない、業界内での繋がりがあるのだろう。
ソロでは多重録音で作り込んだミニマムなポップ・ソングを、Utopiaではメロディックな特性を生かしつつ、壮大なテーマを掲げたアメリカン・ハード・プログレを。その時の気分によって、表裏一体の活動を並行してゆくのが、当時のトッドの初期構想だった。
アルバムごとにコンセプトがコロコロ変わるのがこの人の特徴なので、「別に分けなくてもよかったんじゃね?」と後年のファンは思ってしまう。「複数のプロジェクトを難なくこなしてる俺」に憧れたんだろうな。
アカデミックな楽理を学んだわけではない人なので、いちいち譜面に書き起こすことはなく、大抵はギターやピアノを前にフフンと鼻歌、そこから展開してゆく、といったスタイルの作曲法である。そんなだからして、楽曲の傾向としてはメロディ主体、コードのルーティンをはずした進行になる。
感性を優先するため、調和やバランスは後回しとなる。なので、後づけとなるコード展開は、どうにも奇妙で不安定なモノになる。だからといって、それが耐え難い不協和音になるわけではなく、むしろそれが突出した個性として、乱調の美を形作ってしまう不思議。
なので、いわゆる職業作家のような器用な人ではない。ドンピシャにハマった時の名曲は数あれど、それと同じくらいハズしまくった曲も、また多い。プロデュース依頼は多いけど、思いのほか楽曲提供というのが少ないのも、その辺に由来する。
自由に、何の制約もなければ、不安定ながら引っ掛かりを残し、琴線に触れるメロディを作れる人である。ただ、これが何かしら縛りを入れたりすると、途端につまらなくなるのも、この人の特徴である。
たとえば、シンプルな3コードのロックンロール。Toddのルーツのひとつであり、どのアルバムにも必ず1曲くらいは入っているのだけど、これのハズし率は結構高い。先人によって開拓し尽くされた黄金コード進行は、メロディ先行のToddの奔放さとは相反するものだ。本人は演奏してて楽しそうだけど、これがまた、どうにも凡庸な仕上がりになることが多い。
70年代の英国ミュージック・シーンで勃興したプログレッシブ・ロックは、一時活況を呈したけど、本国でのピークはほんの数年だった。英国では旧世代の遺物として、パンクに一蹴されたプログレだったけど、「何となく知的に見えるロック」というコンセプトは、多くのインテリもどきの共感を呼んだ。その後、世界各国へ拡散されたプログレは、それぞれ独自の変化を遂げる。
ヨーロッパ諸国では、クラシックを由来としたシンフォニックなサウンドが大きくフィーチャーされ、後に換骨奪胎されて心地よいBGMへと退化、スピリチュアル風味を加えたニューエイジへ昇華してゆく。プログレとも親和性の高いミニマル・ミュージックの下地があったドイツでは、KraftwerkやTangerine Dreamなど、プログレよりもプログレらしいアブストラクトな音楽が続々誕生する。
日本では当初、バカテクと理屈先行のCrimson人気が高く、ジャズとの融合によってクロスオーバー的な展開を見せた時代もあったけど、次第に毒気が抜けてニューエイジと大差なくなり、理屈の行き先を失った挙句、アニソンへ取り込まれていった。
で、海を渡ったアメリカでは。
ヨーロッパほどクラシックも根付いてないし、小難しい理屈はウケが悪い。Grateful Deadに端を発する、やたら長くて眠くなる曲のニーズはあるけど、それだってドラッグありきの話だし。どっちにしろ、純粋プログレとアメリカ人とは、相性が良くないのだ。
なので、「人生の意義」や「葛藤」など、そういったしちめんどくさい主張はひとまず置いといて、テクニカル面や組曲志向は残しとこう。そこにわかりやすいハードロックのダイナミズムを持ち込んじゃえば―。
あっという間にアメリカン・ハード・プログレのできあがり。
コンセプト?なんかほら、あるじゃん。「太古の謎」とか「宇宙の神秘」とか。適当にデカいスケールのテーマ、でっち上げときゃいいんじゃね?さらにアルバム・ジャケットを幻想的なイラストで飾れば、もう完璧。
初期のKansas やRush なんかはまだ真面目にやってたけど、次第に大作主義は少数派となり、4分台の曲が多くなる。ラジオでのオンエアを考えると、自然、曲はコンパクトんせざるを得ない。
それが、俗に言う産業ロック。Journey やStyxなんかが、代表的アーティスト。ここまで来ると、原型がなんだかわからない。
Toddもまた純正アメリカ人ゆえ、選んだコンセプトは「太陽神」やら「宇宙の神秘」やら、壮大でドラマティック、スケール感の大きい題材を取り上げている。他国プログレとの違いが、ここで大きく浮き彫りとなっている。
対象を自身以外の「外部」に求めるアメリカに対し、特にヨーロッパ諸国のプログレはインドア志向、深淵たる「内面」へ向かって、深く掘り下げてゆく。ミニマル主体のドイツなんかだと、フレーズの無限反復やドローン音から誘発される不安によって、ゲシュタルト崩壊しちゃってるし。
「わざわざ掘り下げるほど、内面なんて詰まってない」と開き直っちゃってるのか、それとも「内面なんて知りようがない」と合理的に判断しちゃってるのか。
「宇宙炎に関する論文」?
すごくファジーなテーマだよな。
Initiation
posted with amazlet at 18.04.06
Todd Rundgren
Rhino (1990-10-25)
売り上げランキング: 513,563
Rhino (1990-10-25)
売り上げランキング: 513,563
1. Real Man
この時期の代表作として、大抵のベストには収録されているスペーシー・ポップ。ソロ名義ではあるけれど、キーボード3名体制だった初期Utopia布陣でレコーディングされている。バンド初期は正統プログレ・スタイルを志向してため、こういったコンパクトでポップな曲は、ソロに振り向けられることになった。ドラムがちょっと大味だけど、響きが80年代っぽくて、それはそれで俺は好き。ヴォーカルへのコンプのかけ方とかを聴いてると、John Lennonっぽく聴こえる瞬間もある。
シングルとしては、US最高88位。
2. Born to Synthesize
ちょっとエスニックっぽい演出のアカペラ・チューン。俺的に、「アフリカ奥地に住む現地民族にシンセサイザーをあげたら、こんな感じに仕上がっちゃった」イメージ。
ヴォーカルにいろいろエフェクトかけまくってサウンドの一部とする発想は、後の『A Cappella』で生きてくる。
オーソドックスなアカペラ・スタイルではなく、ちょっとエキセントリックなヴォーカライズが下地となっているので、その辺はやはりひと捻りしないと気が済まない性分があらわれている。
3. The Death of Rock and Roll
Toddのロックンロール・チューンの中では珍しく良質の、それでいて突き抜けたアホらしさ。だから良い。ロックなんて結局、知的要素とは相反するものだ。
ギタリストのRick Derringerがなぜかベースで参加しており、それがToddのロック魂に火をつけたのか、いい感じのスタジアム・ロックに仕上がってる。
繊細さのかけらもない、大味なロックンロール。本職のDerringerを押しのけて、ガンガンギターを弾きまくってて楽しそう。
4. Eastern Intrigue
アメリカ人考えるところのオリエンタル・テイストが充満する、なんともインチキ臭漂うポップ組曲。「Easten」と銘打っておきながら、アジアと言っても中近東や、ずっと飛んでスコットランド民謡っぽさもあり、いろいろとごちゃまぜ。なので、「Todd流無国籍サウンド」と言った方が近いかも。マントラみたいなコーラスも入ってるし、お得感満載の幕の内弁当。
でも、そんな未整理感こそが、Toddの魅力のひとつであることもまた事実。この人にきっちり整理されたモノを求めるのはお門違い。
5. Initiation
ドラムにRick MarottaとBernard Purdieが参加。いわゆるプロの職人肌の人たちで、こういうメンツになると、途端にサウンドがプロっぽくなる。大抵、Toddがリズム刻むと揺れまくって安定しないんだけど、ファンとってはそれもまた「独特の味」となっており、逆にこのように「ちゃんとしている」と違和感を感じてしまう。
プログレの人たちがシングル・ヒット狙いを余儀なくされ、3分間ポップスに挑んだのがAsiaだけど、あそこまでメロウに寄ってるわけではなく、ここで展開されるサウンドはもっとストイック。ちゃんとそれぞれのパートの見せ場も作り、それでいてメロディはしっかりポップ。いつもはもっとシックなプレイのDavid Sanbornも、血が騒いだのか、ここでは白熱のブロウを披露している。
6. Fair Warning
Toddお得意のフィリー・ソウルのスケール感を広げ、さらに力強く仕上げたのが、これ。なぜかEdgar Winterがサックスで参加。あんまり聴いたことないけど、Edgar Winterといえば、ギタリストというイメージが強かったのだけど、いやいやここでは本職顔負けのメロウなプレイ。むしろ、こっちの方がSanbornっぽい。
ラストが「Real Men」のサビへとループしてフェードアウト、構成も言うことなし。
このA面のコンセプトでB面も統一しちゃってよかったはずなのだけど、むしろこっちは片手間仕事。やりたかったのはB面だったのだ。まぁひねくれてること。
7. A Treatise on Cosmic Fire
35分に及ぶ一大絵巻、ほぼToddの多重録音による大作。レコードB面を埋め尽くす全編インストを、きちんと対峙して聴き通すのは、相当の難行。俺もちゃんと聴いたの一回きりだし。
シンセを主体とした、「シンフォニックかつドラマティックな組曲をやりたい」と思いつきが先立っており、多分コンセプトは後付け。前述したように、何となく壮大なテーマをぶち上げたかったんじゃないかと思われる。そこまで深く思い詰める人じゃないし。
Utopiaでやってみようと思ってデモ・ヴァージョンを作り、ちょっと足りないところをRoger Powellに手伝ってもらったら、「あれ、これでもう完成じゃね?オレ天才」てな感じだったんじゃないかと思われる。
大方のアメリカ人同様、プログレという「思想」ではなく「スタイル」から入ったToddであるからして、ここでは彼が思うところの「プログレっぽさ」が、これでもかというぐらいにまで詰め込まれている。「シンセがピャーッと鳴って、時にはハード、時には切なくギターを弾いて、なんとなく高尚なヤツ」。こうして言葉にしちゃうと、なんか身もふたもないな、大味すぎて。
中盤のドラムン・ベースっぽいサウンドは、久しぶりに再聴してみての新たな発見。終盤のドローン音やSFっぽいエフェクトは、それこそフォーマットとしてのプログレ的展開。
プログレに限らず、奇想なアイディアがいっぱい詰まっているトラックのため、律儀に通して聴かなくても、好きなパートだけ抜き出して聴くのも、ひとつの方法。何しろ長いしね。
CDで聴いてるからそれほど気にならないけど、多分これ、レコードで聴いてたら、終盤なんて音質悪かったんだろうな。内周ギリギリまでこんなに詰め込むと、音はもう潰れまくり。
ちなみに、これでレビュー299回目。
300回目突入記念で、次回から2回に分けて特別企画を実施します。
乞うご期待。
TTodd Rundgren - The Complete Bearsville Albums Collection
posted with amazlet at 18.04.06
Todd Rundgren
Rhino (2016-02-26)
売り上げランキング: 57,968
Rhino (2016-02-26)
売り上げランキング: 57,968
At the BBC 1972-1982
posted with amazlet at 18.04.06
Esoteric Recordings (2014-11-10)