 1996年リリース、90年代UKでの大衆バンド路線を確立した5枚目のオリジナル・アルバム。80年代ネオアコ=ポップの潮流として位置付けられていた前作『Miaow』は、叙情性とペシミズムのカクテル・シェイクがライト・ユーザー層も取り込んで、ダブル・プラチナム獲得に至ったけれど、キャリアの中ではまだ序章。一家に一枚に行き渡るまで裾野を広げたのは、その次の初期シングル・コンピ『Carry On up the Charts』から。予期せぬお茶の間路線へのシフトチェンジによって、その後はサウンドもよりポップ性を強め、なんと5枚のプラチナム獲得となったのが、このアルバム。
1996年リリース、90年代UKでの大衆バンド路線を確立した5枚目のオリジナル・アルバム。80年代ネオアコ=ポップの潮流として位置付けられていた前作『Miaow』は、叙情性とペシミズムのカクテル・シェイクがライト・ユーザー層も取り込んで、ダブル・プラチナム獲得に至ったけれど、キャリアの中ではまだ序章。一家に一枚に行き渡るまで裾野を広げたのは、その次の初期シングル・コンピ『Carry On up the Charts』から。予期せぬお茶の間路線へのシフトチェンジによって、その後はサウンドもよりポップ性を強め、なんと5枚のプラチナム獲得となったのが、このアルバム。 UKでは、売り上げ30万枚でプラチナム認定となるので、単純計算で言えば「かける」5で150万枚、これを日本に置き換えると、人口比率では日本がほぼ倍となるので、ざっくり300万枚のセールス効果、といった具合。同時代のGLAYやglobeに匹敵する、と言えばわかりやすいのかな。いや、伝わりづらいよな。
だからと言って、そんな英国での持てはやされ振りが日本で紹介されたわけではなく、せいぜいロキノンやクロスビートあたりに、インタビューやディスク・レビューが掲載される程度だった、というのが、リアルタイムで追っかけてた俺の印象である。
扱いとしても、せいぜい半ページか4分の1ページくらいで、極東のファンは不遇を囲っていたのだった。まぁでも考えてみりゃ、サエないオッさんバンドより、ブリットポップやTake Thatあたりに力を入れちゃうのは、商売的に仕方のないことで。
これは日本のメディアの取り上げ方が大きく影響しているのだけれど、Beautiful South といえば、前身のHousemartins繋がりで語られることが多く、いまだにネオアコの範疇にカテゴライズされたままでいる。いや確かに間違ってないし、実際、来日したのも2枚目の『Choke』リリースの頃なので、アーティスト・イメージがその時代のままで止まっちゃってるのは致し方ないのだけど、も少し中期以降に目を向けてもいいんじゃない?と俺は言いたいのだ。
再発されるアイテムといえば、ネオアコのくくりでのデビュー・アルバム、またはせいぜい『Choke』までだし、それ以降のアルバムは置き去りにされている。どのアルバムも、ほぼ初回リリース以降、国内盤は流通していないはずである。UKではむしろ、圧倒的な支持を集めているのは中期以降なのに。なんだこの温度差は。
お茶の間路線を「迎合」と受け止めて黙殺する、日本の洋楽メディアのスノッブ路線って、昔から変わらないよな。
ま、UKも似たようなもんだけど。
大ブレイクのきっかけとなった『Carry On up the Charts』がリリースされた経緯というのは、よくあるレーベル・サイドの営業的要請ももちろんあるけど、それよりもむしろ、女性ヴォーカルの変更という、言ってしまえば社内人事に依るところが大きい。
デビュー当初から在籍していたBriana Corriganがバンドを去ることになり、キャリアの区切りとして、ベスト・アルバムの企画が立ち上げられた。もともとは真っ当なポップ・シンガーを目指していたBriana、メジャーで活動できることに不満はなかったけど、自身とバンドが目指していた方向性のズレが広がってしまったため、友好的なパートナーシップ解消となる。
ただ実際のところは、「こんなエログロな歌詞もう歌いたくないわ」とバックレちゃったのが真相らしい。そりゃ、メロディは流暢なポップなのに、猟奇殺人や資本主義を皮肉った内容ばかり歌わされてりゃ、次第に病んでくるのも仕方がないわけで。
で、2代目ヴォーカルとして加入したのが、その後の全盛期を支えることになるJacqui Abbott。「クラブで歌っていたのを耳にしたPaul Heaton がその声に惚れ込んだ」という、何だか真っ当すぎて逆に怪しく感じられる経緯だけど、取り敢えず当初はお試し期間として、加入するに至る。
どちらかと言えば、見た目も中身も骨太なJacquiであったため、ビジュアル的な貢献度は薄かったけれど、まぁそれでも紅一点ではある。むさ苦しい労働者階級然とした中年オッさんバンドとしては、加入してくれるだけ、そして「若い」というだけで充分だった。
当時のトレンドであった、OasisやBlurを始めとするブリット・ポップ勢と比べ、相当ねじれた世界観を持つ彼らの歌詞を受け入れてくれる女性シンガーは限られていた。もう歌ってくれるだけで充分なはずなのに、基本もしっかりしているし多彩な表現力も持ち合わせている。
一体これ以上、何を求めろというのか?フェミニンなルックスやファッションまで求めるのは、それこそ虫が良すぎるというもので。
取り敢えず、互いの適性・力量を探るため、ちょっと毒を抑えて制作されたのが『Miaow』だったとすると、そのリミッターを外しちゃったのが『Blue is the Colour』である。ミーティングを重ねてお互い手の内も見えてきて、「NGワードはなさそうだな」というソングライター・チームの判断のもと、一時抑えていた皮肉も自虐もエログロも、一気に放出した。だって、冒頭からいきなり近親相姦がテーマだもの。よくオッケーしたよな、Jacquiもレコード会社も。
どんなエグいテーマでも易々と歌いこなしてしまうJacquiのヴォーカル・スタイルを受け、調子に乗ったソングライター・チームはさらに歌詞の過激さ・エキセントリックさをエスカレートさせてゆく。それに伴って、彼らのサウンド・コンセプトもまた微妙に変化してゆく。
過激なテーマを過激なサウンドで飾るのではなく、様々な悪意を濃縮還元した言葉・ストーリーを、幅広い年齢層に対応したコンテンポラリー・サウンドでコーティングする。考え方としては、ハードコア・パンクとの対局にあったネオアコと同じロジックである。
初期のBriana在籍時は、Housemartinsという前置きがあったため、その延長線上で「ちょっとポップなネオアコ・サウンド」というコンセプトだったのが、キャリアを重ねるにつれ、ネオアコ色は後退していった。そしてJacqui加入を機に、バンド・サウンドにこだわらないサウンド・アプローチを志向するようになる。曲によってはほぼストリングスだけで構成された曲もあったりして、バンドのアイデンティティが問われたりもする。
普通そうなると、バンドの存在意義が薄くなりがちだけど、実際のところはBeautiful South、もともとそういった特性を持つバンドである。一般的なロック/ポップ・バンドと比べると、アーティスティックなエゴがほとんどない人たちの集まりである。
デビュー当初から、Paul Heaton & Dave Hemingwayのソングライター・チームがイニシアチヴを握っており、その彼らプラス歴代女性ヴォーカルとのアンサンブルがセールス・ポイントとなっている。なので、バンドの存在感はあんまりない。最初から存在感は薄かったし、それは解散に至るまで変わることはなかった。
よほどのコアなファンであっても、演奏陣のフルネームを言える者がほぼ皆無であることも、このバンドの特殊性を象徴している。それならいっそ、ユニット形態にしちゃってスタジオ・ミュージシャンを使った方が仕上がりも良いし効率も良さそうだけど、誰もそんなことは思わなかったようである。ライブが好きな人たちなので、演奏陣がいなきゃいないで困ってしまうのだ。まぁみんな気が合うんだな。
いわゆる名プレイヤーがいるわけでもなければ、「白熱のギターソロ」なんてクライマックスがあるわけでもない。「盤石のリズム・セクション」やら「ツボを押さえたインタープレイ」やら、そういったバンド・マジック的なストーリーにも、あんまり興味はなさそうである。彼らは常に淡々と、自身のパートを確実に演奏するだけだ。
Blue Is the Colour
posted with amazlet at 17.08.16
Beautiful South
Ark 21 (2000-03-07)
売り上げランキング: 1,007,194
Ark 21 (2000-03-07)
売り上げランキング: 1,007,194
1. Don't Marry Her
本文でも書いた、おそらく彼らの作品の中で最も過激なテーマであり、そして同時に最も抒情的かつポップ性の強いナンバー。前途有望な、加入したばかりの女性シンガーに「Fuck Me」と歌わせてしまうHeaton。それは屈折した愛情表現だったのか、それとも純粋にアーティスティックな発露に基づく結果だったのか。
もちろん英国人のことだから、そんなギャップを平然と受け止め、2枚目のシングルとしてUK最高8位。やっぱ英国人、こんな人ばっかり。
2. Little Blue
こちらも抒情的かつ爽やかなアコースティック・ポップだけど、Google 翻訳で「Striding Snail = ストライドカタツムリ」という言葉が出てきたので、これまた画像検索で調べてみると…、見たことを後悔してしまう、グロい巨大カタツムリの画像だった。あまりにサウンドとそぐわぬ言葉の選び方こそ、彼ら英国人の特性なのだろう。
3. Mirror
Jacquiによるソロ・ナンバー。ソフトな発音の彼女が歌うと英語特有の角が取れて、時にフランス語っぽく聴こえてしまう瞬間がある。ラス前にHeatonがボソボソモノローグを付け加えているのは、保護者的な役回りか。
4. Blackbird on the Wire
アルバムから3枚目のシングルカット、UK最高23位。以前にもどこかで書いたけど、彼らのバラードの中では3本の指に入る名作だと思うのだけど、それほど人気が集中しているわけでもない。やっぱ初期楽曲に集中しちゃうんだよな、こういうのって。
Paul McCartneyが歌ったBlackbirdは前向きの姿勢だったけど、ここでのBlackbirdは陰鬱と自虐が交差している。でもそれが英国人のひとつの側面なんだよな。同じイギリスなのに、どうしてこんなに違うのか。
5. The Sound of North America
Elvis PresleyやFrank Sinatraなど、かつての黄金時代アメリカのポップ・イコンを思いつく限り書き連ね、そこに英国人視点を継ぎ足したポップ・バラード。もちろん彼らのことなので、聴く限りでは全然アメリカっぽくない。
Paddy McAloonはこの時代のアメリカへの憧憬を包み隠さず賛美して、珠玉の楽曲を作った。そこにあるのは無為の姿勢であり、皮肉や憐憫なんてものはない。彼らとPaddyの違い、それは神への向き合い方、リスペクトの姿勢だ。
6. Have Fun
こちらもまったり緩やかなポップ・バラード。なぜか時々DylanっぽくなるHeatonと、堅実なスタイルを崩さないJacquiとのデュエットで構成されてる。決して大ヒットする性質のサウンドではないけれど、ちょっと疲れた時なんかに聴くのもおすすめ。
7. Liars' Bar
ブルース・タッチにまとめられた飲んだくれの歌。ブルース・スケールを使っているのに、ヴォーカルだってまるでTom Waitsそっくりだというのに、全然黒っぽさを感じさせない。そこがまた、このバンドの特性をくっきりと浮かび上がらせている。
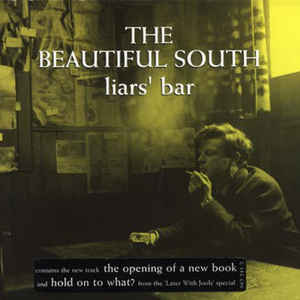
8. Rotterdam (or Anywhere)
ギターのリフが印象的な、Jasquiによる軽快なポップ・バラード。先行シングルとしてもリリースされ、UK最高5位をマーク。ストリングスと小技としてのメロトロンが郷愁を誘う演出。「あなたの中のロッテルダムはどこにでもある」という、何だかよくわからない内容だけど、下手なツッコミも霞んでしまうほど、メロディ・ラインが流麗。
9. Foundations
この時期の彼らにしては珍しく、ホーン・セクションをフィーチャーしたグル―ヴィ・チューン。徹底的に漂白したモータウン・ナンバーといった趣きで、まぁこういったのもアリか、といった仕上がり。
10. Artificial Flowers
彼らにしては皮肉も自己憐憫もないナンバーなので、逆に同化しちゃったのかと思ってたら、古いカバー曲だった。1952年Bobby Darrinによるベタなバラード。オールディーズの人なので、俺も名前くらいしか聞いたことないしYouTubeにも転がってないしで、比較できなかった。まぁこういった直球のメロウもアリか。
11. One God
各方面でアンモラルをまき散らしている彼らがストレートに神を題材として取り上げるなんて、と思ってたら「2人いるかもしれない、いやもしかしたら3人かな?」って、やっぱりいつもの彼らだった。たまには「君こそ僕の神よ」とか、クサく歌い上げてみろよとまで思ってしまう。
12. Alone
ラストは彼らに不似合いなブルース。もしかしてこの時期、アメリカ進出でも狙っていたのかな。いやないか、彼らの言葉のニュアンスを、アメリカ人が理解できるとは思えないし。
Carry On Up The Charts: The Best Of The Beautiful South
posted with amazlet at 17.08.16
Beautiful South
Fontana Island (1995-10-09)
売り上げランキング: 394,862
Fontana Island (1995-10-09)
売り上げランキング: 394,862
THE BBC SESSIONS
posted with amazlet at 17.08.16
BEAUTIFUL SOUTH
MERCU (2007-06-19)
売り上げランキング: 452,634
MERCU (2007-06-19)
売り上げランキング: 452,634








