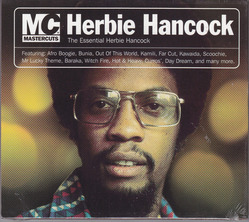クラブ・ジャズやレア・グルーヴ系のコンピではもはやクラシックである”Cantaloupe Island”、あまりにもサンプリングされまくったため、最早ベタすぎてまともに取り上げられることもなくなってしまったHerbie。スタンダード・ジャズをキャリアのスタートとして、Milesスクールの門下生として名を上げ、その後はフュージョンの先駆けとなった”Watermelon Man”から連なるエレクトリック路線と、VSOPに代表されるアコースティック路線の双頭体制でもって現在に至っている。
クラブ・ジャズやレア・グルーヴ系のコンピではもはやクラシックである”Cantaloupe Island”、あまりにもサンプリングされまくったため、最早ベタすぎてまともに取り上げられることもなくなってしまったHerbie。スタンダード・ジャズをキャリアのスタートとして、Milesスクールの門下生として名を上げ、その後はフュージョンの先駆けとなった”Watermelon Man”から連なるエレクトリック路線と、VSOPに代表されるアコースティック路線の双頭体制でもって現在に至っている。 50年代のモダン・ジャズ全盛期から活動している人なので、ピアニストとしてレジェンド・クラスなのだけど、そのメインであるはずのピアノへのこだわりはそれほど強いわけでもないらしく、純粋にピアノをメインとしたアルバムはキャリアを通じてほぼ半数くらいである。デビュー当初はともかくとして、Milesから独り立ちした後はコンポーザー的ポジションの作品が多く、それはTVサントラなどの片手間っぽい仕事から全編ゲスト・ヴォーカル入りの単なるR&Bアルバムまで多岐に渡る。そしてその中には『Future Shock』のように、大々的にヒップホップを導入したアルバムもあり、バラエティに富んでいる。ていうか支離滅裂なディスコグラフィーである。
近年はもっぱらアコースティックの方に傾倒しており、ポピュラー・シーンのゲスト・ヴォーカルを迎えてのコラボを積極的に行なっている。いずれもジャズ・アルバムとしては近年稀に見るヒットとなっており、実際どの作品もクオリティは高い。Joni Mitchellを大々的にフィーチャーした『River』がグラミーを獲得したのは記憶に新しい。
Robert Glasperを始めとして、別ジャンルのアーティストとのコラボというのは近年のメインストリーム・ジャズの流れなのだけど、なるべく音楽性がかけ離れているほど、接点が遠ければ遠いほど、面白い作品ができる傾向にある。そりゃそうだよな、ジャズのアーティストとやったって、ただのジャム・セッションに過ぎないし。
経歴だけ見ればジャズ本流、それでいていつまでも先鋭性を失わない人なので、一般的なポピュラー・シーンには馴染みが薄かったはずなのだけど、その強烈すぎるインパクトが日本のお茶の間レベルにまで浸透しちゃったのが『Future Shock』、もっと言ってしまえば”Rock It”である。
既視感を伴う70年代少年雑誌的近未来感を具現化した斬新なPVはGodly & Creme監督によるもので、今でもMTVクラシックスとして燦然と輝いており、多分何がしかの形で目にした人は多いはず。クレイ・アニメを効果的に使った映像はアバンギャルドでありながら可愛らしさも秘めており、何が何だかわからないけど、多くの人の印象に残ったのは確かである。
それにも増して、当時はほんとアンダーグラウンドでメチャクチャ尖っていたBill Laswellにサウンド・メイキングを依頼するというのも、かなりの冒険だった。そのアバンギャルド性はMick Jaggerを始めとして、多くのミュージシャンから羨望の的だったけど、ポピュラリティのある類のサウンドではなかったはず。小田和正がデスメタル・バンドとコラボするようなもの、と言ったらわかりやすいだろうか。
音楽史的には「ジャズとヒップホップの融合の走り」として位置付けられているこのアルバム、サウンド的にはプロデューサーBillの色が強く、彼が主立って制作したヒップホップ・リズムのバック・トラックにHerbieによるフュージョン・テイストのシンセを被せるのが、全編を通しての基本パターンとなっている。その主役であるはずのHerbieだけど、それほどソロ・プレイを強調するわけでもなく、ほんとまな板の鯉、素材として調理されることを普通に受け入れている。
ただ、ここで披露されたアバンギャルドなサウンドは皮肉なことに、世間一般が思い描く「前衛的なサウンド」の典型として認知されてしまい、『ミュートマJAPAN』のSEから始まり、さんま御殿の現在まで「わ、アバンギャルドね♡」といった風に続いている。
Herbieとしては、あくまで時代のトレンドの一歩か二歩先を行くサウンドを志向していたのだろう。『Head Hunters』をリリースして世間をあっと言わせたように、ジャズにもロックにもカテゴライズできないいびつな音楽をドヤ顔で提示して見せたのだけど、思いのほかジャズ以外、むしろ日常的にそれほど音楽に関心のない層にまで浸透してしまい、結果的にあれよあれよとグラミー獲得までの大ごとになってしまった次第。
ただそこでレコード会社、そしてHerbie自身も大ヒットを受けてこの路線に味を占めてしまい、二番煎じ三番煎じを狙って同コンセプトのアルバムを乱発することになるのだけど、リリースごとにセールスは緩やかな下降線を辿ることになる。あくまでインパクト勝負、時を経て熟成される類のサウンドではないので、そりゃ当たり前。何度もやっちゃうと飽きるよな、そりゃ。
こういう場合、ただの一発屋なら時代の徒花として、そのままフェードアウトしてゆくのだけれど、そこは優秀なサウンド・コーディネーターのHerbie、一旦エレクトリック路線を休止して原点回帰、再びアコースティック・ジャズの世界へ回帰してゆくのだけど、まぁそれはもう少し後の話。
Future Shock
posted with amazlet at 16.02.12
Herbie Hancock
Sbme Special Mkts. (2008-03-01)
売り上げランキング: 17,868
Sbme Special Mkts. (2008-03-01)
売り上げランキング: 17,868
1. Rock It
世間一般にレコードのスクラッチ・ノイズが認知されたのは、多分この曲が最初。レコードを録音・再生媒体としてでなく、音の出る『楽器』として擦って音を出すという発想は、物を大事に取り扱う日本人からは出なかったと思う。
Billの作った基本リズム・パターンにHerbieが最新鋭フェアライトCMIの音色を乗せるという、まさしく80年代的トレンドど真ん中直球の音である。そこにGrand Mixer DXTによるスクラッチをエフェクト的に挿入、重たいディストーション・ギターはエレクトリック・マイルス末期で弾いていたPete Coseyによるもの。
2. Future Shock
タイトル曲はDwight Jackson Jrによるファルセット・ヴォーカル入り、こちらはファンク・マスターでお馴染みCurtis Mayfieldのカバー。Curtis自身がファルセットで歌ってるのに、このHerbieヴァージョンもファルセットを使用するのは、ちょっと芸がないんじゃない?と思ってしまう。
オリジナルは重心の低い真っ黒などファンクなのに、Herbieのヴァージョンは普通のダンサブルなR&B。ただダンスフロア向けには、こちらの方が重過ぎなくてウケが良いと思う。適度に洗練されている方が、ポピュラリティを獲得しやすい好例。
3. T. F. S.
リズムの立ったフュージョンといった趣きの、どちらかといえばHerbie主導と思われるナンバー。ベシャッとしたリン・ドラムの8ビートが、今となってはダサいのを通り越して新鮮に聴こえ、独自の音空間を形成している。
エレクトロ・サウンドと生ピアノとの絶妙なブレンド具合は、やはり自ら現役ミュージシャンであるBillの匙加減の妙。
エレクトロ・サウンドと生ピアノとの絶妙なブレンド具合は、やはり自ら現役ミュージシャンであるBillの匙加減の妙。
4. Earthbeat
東南アジア系のフレーズ・リズムをフェアライトでプレイした、ノスタルジックを感じさせる小品。YMOとヒップホップのハイブリットと言えば分かりやすいだろうか。YMOもこのくらい「わかりやすい前衛」を突き詰めてゆけば、英米でのブレイクももうちょっと大きかったと思うのだけど、そこは各アーティストのこだわり具合の違いだろう。
ディスコ、クラブでプレイされても違和感がなく、しかもきちんとへヴィ・リスナーにも探求の余地が残されている、ある意味すっごく「親切な」曲。
5. Autodrive
Bernard Fowlerのシャウトがサンプリングで「これでもかっ」というくらい使われている、こちらもわかりやすい「アバンギャルド・サウンド」。当時、サンプリングという手法はお茶の間的にも分かりやすいインパクトがあったため、犬猫の鳴き声をサンプリングしてメロディをつけたアルバムが発売されたくらい浸透していた。しかもそれがそこそこ売れてしまったことも、TVのワイドショーで見た記憶がある。
Herbieの色が強く出ている曲で、もちろんリズム・ループもクールなのだけど、やはりリード楽器である鍵盤を自在に操るHerbieのテクニックが炸裂している。最新鋭のあらゆるおもちゃに囲まれて、嬉々としてプレイする彼の姿が目に浮かぶ。
6. Rough
無機的なエレクトロ・ファンクに仕上がっており、そこに適度にソウルフルなLamar Wrightによるヴォーカルがスキャット的に使われている。かなりBill色の濃いトラックに仕上がっており、この機械的なリフレインが当時はダンス・シーンで好評だったのだろう。
人力リズム特有の「揺れ・ゆらぎ」を極力排し、あくまでジャストなリズム・パターンの円環構造によって、思考能力を解放、肉体性を訴求させる暴力衝動。ラストを締めるのに最適な選曲。
Herbie Hancock: The Complete Columbia Album Collection 1972-1988
posted with amazlet at 16.02.12
Herbie Hancock
Sony Legacy (2013-11-12)
売り上げランキング: 13,384
Sony Legacy (2013-11-12)
売り上げランキング: 13,384
ハービー・ハンコック自伝 新しいジャズの可能性を追う旅
posted with amazlet at 16.02.12
ハービー・ハンコック
DU BOOKS
売り上げランキング: 204,542
DU BOOKS
売り上げランキング: 204,542