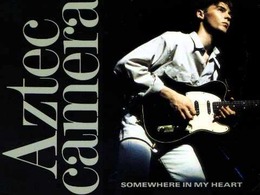1990年リリース、Aztec Camera4枚目のアルバム。文化系男子の中性的フェロモンを発していたネオ・アコ・サウンドから一転、大幅にメジャー・サウンドを意識したアーバン・ソウル的な秀作『Love』からは3年のブランクが空いている。
1990年リリース、Aztec Camera4枚目のアルバム。文化系男子の中性的フェロモンを発していたネオ・アコ・サウンドから一転、大幅にメジャー・サウンドを意識したアーバン・ソウル的な秀作『Love』からは3年のブランクが空いている。 前作に引き続き、唯一のメンバーRoddy Frame以外のミュージシャンはすべて外部起用、すっかり彼のソロ・プロジェクトとして定着したAztec Cameraだけど、このアルバムはUK最高22位と、緩やかにセールスのピークを過ぎていた頃である。
時代はマッドチェスター・ムーヴメントの真っ只中、イキのいい若手(とは言っても、実際はそれほど若くなかったけど)のStone RosesやHappy Mondaysやらが台頭してきて、ハウス・ビートとオルタナ系ロックとのハイブリッドが幅を利かせつつあった頃である。
Roddyもまた、『Love』でアメリカのブラコン・サウンドを移植した横揺れビートを導入していたけど、終末感を漂わせた暴力的なリズムの前では太刀打ちできず、この『Love』をピークとして、チャート・アクション的には次第に地味になってゆく。
ニュー・ウェイヴ・ムーヴメント終了後の80年代初頭からインディー・シーンで活動していたギター・メインのバンドということで、どうしてもネオアコの範疇で語られることの多いAztec Camera、ていうかRoddy。
とは言っても、ほんとにステレオタイプなネオ・アコ・サウンドを展開していたのは、初期の2枚しかない。なぜかMark Knopflerをプロデューサーに迎えた初期の傑作『Knife』が、そのネオ・アコ的サウンドの集大成とも総決算とも言える出来栄えだったため、もうこの路線においてはやり尽くしてしまった感が強い。
そういった経緯もあって、3枚目の『Love』では新機軸として、80年代ブラコンのメロウ&エモーショナルなMOR的サウンドを導入、セールス的にもキャリア最高の売り上げ計上に至った。最初は戸惑いもあったファンからも次第に理解を得、しばらくはこの路線で行くのだろう、と誰もが思っていた。いたはずなのだけど、変わりゆく音楽シーンの傾向に合わせようとしたのか、それともミスマッチ感の強いダンサブルなサウンドに違和感を覚えたのか、その後は音楽性が定まらず、遂にAztec Camera終了まで迷走状態に陥ってしまう。
なので、この『Stray』にも言えることだけど、よく言えばバラエティに富んだ音作り、意地悪く言ってしまえば、まとまりなくとっ散らかった印象が強い。
Roddyの人間性として、今で言う「意識高い系」というのか、もう50歳を過ぎているにもかかわらず、いまだ「永遠のアダルト・チルドレン」的要素が強い。どうやっても現状に満足せず、ひとつところに落ち着かず、すぐに自分探し/自分磨きの旅に出てしまうのが、当時のRoddyに見られる特徴である。日常では役に立ちそうもない資格の勉強をしたり、Facebookに雲やラテアートの写真をアップしてしまうアラフォー女子の如く、傍から見るとちょっとイタイ人でもある。
まぁそんなスキだらけなところが母性本能をくすぐるため、昔から女性ファンが多い証でもある。
反面、レーベル側としてはイメージが定着しないため、積極的にプロモートしづらくなる。特にこの『Stray』では、ひとつのアルバムの中でもコロコロ曲調が変わるので、セールス・ポイントが絞りきれず、結局はいつも通り、「ネオアコの旗手による意欲作」など、どうにもフワッとしたキャッチ・フレーズでお茶を濁してしまうことになる。
ダウンロード販売が主流となって、アルバムというフォーマットの意味自体が薄れかけている現在なら、それはそれで良いのだろうけど、当時はまだアルバム・コンセプトが重視されていた時代である。国内盤発売の担当者や輸入盤のショップ店員も、さぞかしPOP作成に苦労したんじゃないかと思われる。
メジャー・レーベルへの移籍によって、レコーディング環境や販促体制の充実というメリットを手に入れたはいいけど、そこから方向性に行き詰まってしまったのが、90年代のAztec Cameraである。
レーベル側としては、ネオアコ界のトレンド・リーダーとしての才能と可能性を見出だし、でもそれだけじゃ世界戦略的にはちょっと弱いので、時流に合わせたブラコン・サウンドの意匠を嵌め込んで、キャッチーさを演出してみた。結果としてはキャリア最高のセールスを叩き出し、みんながwin-winで収まるはずだったのだけど、そこで今で言う中二病をこじらせてしまったのが、肝心のRoddy。これまでの「悩める思春期モラトリアム」から一転、リア充よろしく精いっぱいチャラくしてみたつもりだったけど、どこか居心地の悪さ、無理やり感は拭えなかった。所詮は、「どこかヘタレ感の漂う文系男子」である自分を客観視してしまったんじゃないかと思われる。
どこかにあるはず、もしかすると、自分のすぐ足元にあるかもしれない、自分にしっくり来る理想のサウンドを追い求める、そんなRoddyの試行錯誤が如実に記録されているのが、このアルバムである。
拳を振り上げたくなるストレートなロック・ナンバーから、しんみり聴き入ってしまうバラードまで、サウンドはバラエテイに富んでいる。前作のようなブラコン要素は薄く、むしろ『Knife』のビルド・アップ・ヴァージョン、叙情性をベースにサウンドをゴージャスにした感が強い。まぁ曲調によってヴォーカル・スタイルを切り替えられるほど器用な人ではないので、どれを聴いてもRoddyのカラーが色濃く現れている。
逆に言えば、どんなサウンドだったとしてもRoddyのパーソナリティは微動だにせず、正しくAztec CameraというバンドがイコールRoddyそのものである、と証明しているのが、この『Stray』である。
この頃からRoddyのライブ・パフォーマンスはバンドを引き連れないソロ・スタイルのセットが多くなり、初期のアコースティック・ナンバーはもちろんだけど、メジャー移籍以降のナンバーから最新曲まで、そのほとんどを自身によるギター弾き語りだけで表現している。「僕がAztec Cameraそのものなんだっ」という自信の顕れでもあるし、まぁ予算の何やかやもあったんじゃないかとは思うけど。
時間と予算をかけて作り上げたサウンドを一旦チャラにして、ライブで披露される素顔のRoddyの歌は、昔と同じ、技巧にあふれた素直なメロディ・ラインを奏でている。どれだけ新奇なアレンジを施そうとも、Roddyの歌が揺るがないのは、曲自体がしっかり作り込まれているから、と言わざるを得ない。それがしっかり伝わってるからこそ、彼のファンは年季の入った人が多い。
多いのだけど、そんな魅力が外部にきちんと発信されているのかと言えば、残念ながら充分とは言い難い。イメージが定まらない、またはネオアコの先入観が強すぎるのも考えものである。
これがDavid Bowieなら、変化してゆくこと自体がコンセプトになるのだろうけど、あいにくそこまでのエゴは少ない人である。結局は良い曲を愚直に演奏してゆくことが一番性に合ってるという、極めて当たり前の結論に落ち着くことになるのだけど、そこに至るまでの若気の至りが、この『Stray』から解散まで、しばらく続くことになる。
Aztec Camera
Edsel Records UK (2012-09-11)
売り上げランキング: 329,721
Edsel Records UK (2012-09-11)
売り上げランキング: 329,721
1. Stray
何のごまかしもない、正統派王道バラードからスタート。ギターとピアノによるシンプルなバッキングで、前作のようなオーバー・プロデュース気味だったサウンドとは一線を画している。
これだけ聴いてると、正々堂々としたアコースティックなテイストで統一されてるかと思いきや、実はバラバラであることを思い知らされることになる。
2. The Crying Scene
エフ クトを効かせたギターを抱えたRoddyが歌うポップ・ロック・ナンバー。ややアメリカン・ロック調なところがあって、時々Bryan Adamsっぽく聴こえる瞬間もあり。甘いマスクは彼と共通するところもあり、もう少し色気づいていれば、彼と同じポジションくらいまではいけたかもしれないけど、まぁ無理か、所詮文科系だし。
シングルとして、UK最高70位。
3. Get Outta London
その細い声質からは想像できないけど、多分Stones辺りをモチーフとして作られたんじゃないかと思われる、Roddyなりのブルース・ナンバー。時々ラウドなギターを弾く瞬間があるのだけど、まぁほどほどの感じで収めているのが、やはりRoddy。この辺が真面目といえば真面目。
”Jump”に近いアプローチだけど、時々こういったのがやりたくなるのだろう。
4. Over My Head
本人曰く、Wes Montgomeryも意識したジャジーなナンバー。1分ほど「らしい」ストロークが続き、なんかこのまま終わっちゃうんじゃないかと思ってしまうほど、イントロだけで十分完結している。
5. Good Morning Britain
このアルバムで一番といえば、やはりこれ。一緒に歌うは元ClashのMick Jones。当時のMickはBig Audio Dynamiteで第2のピークを迎えていた頃で、ロートルにもかかわらず勢いが有り余っていた時代である。
Roddyのポップ性とMickのエモーショナルなロック成分、それにほんのちょっぴりモダン風味のデジ・ロック・サウンド。Roddyとしても憧れだったはずだし、Mickもまたイケイケ状態だったため、若手に胸を貸す心づもりだったのが、案外ウマが合って意気投合し、できあがったのがこのサウンド。
どの場面を切り取ってもいちいちサマになる、80年代ロックの完成形のひとつがここにある。どんな理屈をこねようと、拳を振り上げたくなるような音楽には、誰もかなわない。
US19位は近年を比べても妥当な位置。だけど、もっと売れてほしかったな。
6. How It Is
もろ”Honky Tonk Woman”っぽいギター・リフから始まり、最後までストレートなハイパー・ブルース・ロックを奏でている。こうして最初から聴いてみると、声とサウンドとのミスマッチ感が逆に良い方向へ作用しているのがわかる。
7. The Gentle Kind
ここでやっと、ネオ・アコ登場。この辺は初期っぽいサウンドだな。
バラードでもなく、かといって入念に作り込まれたポップでもない。メロディ・ラインも流麗で、ギターの音色もちょうど良い。『Knife』サウンドの完成形と言っても褒めすぎではないくらい、しっかりした構造なのだけど。
だけど、こんな曲ならRoddy、ササッと作れてしまうのだろう。ネオ・アコの文脈で書かれた曲は、所詮ネオ・アコ村の中でしか通用しない。彼が求めるのは、今までに演じたことのないサウンドなのだ。
8. Notting Hill Blues
ラスト2曲はシンプルなバラードで。あまりに正統派過ぎて、メロディがあまりキャッチーではないのが気になるところ。こういったサビ、日本でも結構パクられてた記憶があるけど、すぐは思い出せない。
9. Song For A Friend
8.よりもう少しギターを前面に出した曲。サウンドはまんまフォークなのだけど、メロディのポップさによって、どこかミスマッチ感が漂っている。いるのだけど、長年のファンなら恐らく気に入ってしまう世界観をを、余すところなく表現している。
Original Album Series: Aztec Camera
posted with amazlet at 16.02.02
AZTEC CAMERA(アズテック・カメラ)
Warner Music (2010-02-27)
売り上げランキング: 84,344
Warner Music (2010-02-27)
売り上げランキング: 84,344