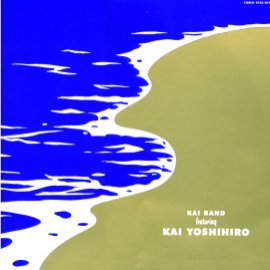1987年リリース、甲斐よしひろ初のオリジナル・ソロ・アルバム。甲斐バンド解散プロジェクト終了から5か月、その余韻が冷めぬタイミングでリリースされたこともあって、オリコン最高3位と、セールス的にも成功を収めた。
1987年リリース、甲斐よしひろ初のオリジナル・ソロ・アルバム。甲斐バンド解散プロジェクト終了から5か月、その余韻が冷めぬタイミングでリリースされたこともあって、オリコン最高3位と、セールス的にも成功を収めた。 当時の日本のバンドとしては珍しく、甲斐バンドはキャリアのピークを保ったまま、終焉を迎えることができた幸福なグループである。まだロック・ビジネスが未整備だった80年代、バンドの解散というのは静かに迎えるものだった。金か女でもめてのケンカ別れか、はたまた人気のピークを過ぎて、ひっそりフェードアウトしてゆくかのどちらかで、いずれにせよ大団円とは言えないものばかりだった。大抵の場合、ちゃんとしたラスト・アルバムやライブが行われることもなく、契約解消で「ハイそれまでよ」といった具合。解散をコンテンツとして捉える視点がまだなかった時代の話だ。
そんな刹那的な流れに一石を投じたのが、YMOの解散だった。解散を前提としたアルバムとライブ、そのプロセスを記録したドキュメンタリー映像や写真集など、彼らが興したコンテンツは、その後の解散ビジネスのモデル・ケースとなった。
NY3部作が進行している最中、甲斐は東芝とのソロ契約を結んでいる。当時の甲斐バンドは、新興レーベル「ファンハウス」の所属だった。バンドとソロで所属レーベルが違うという時点で、なんかキナ臭い交渉や取引があったんじゃないか、と邪推してしまう。
ファンハウスでの甲斐バンドのオリジナル・アルバムは『Love Minus Zero』のみ、実質ワンショット契約で東芝に舞い戻っている。不可解なレーベル移籍劇の詳細は不明だけど、初代社長である新田和長の意向によるものだったことは間違いない。
レーベル立ち上げにつき、知名度のある目玉アーティストをラインナップしたい。ただどのレーベルだって、そう易々とドル箱アーティストを手放したりはしない。なので、日本的な義理人情に訴えかけ、旧知の仲である甲斐に声をかけた、というのを以前のレビューで書いた。
もちろん、甲斐の漢気一本で決められるものではなく、東芝とファンハウスとの生臭い交渉や駆け引きが繰り広げられたことは、想像に難くない。いくら真摯なアーティストとはいえ、浪花節的な義理人情に縛られることだってあるし、政治的なしがらみだってある。人はカスミばかりを喰っては生きていけないのだ。
名義貸しのようなレンタル移籍というミッションを終え、甲斐はソロ・プロジェクトに本腰を入れることになる。
末期の甲斐バンドの収支面は、お世辞にも優良と言えるものではなかった。ネーム・バリューこそ磐石となってはいたけれど、かつてのようなヒット・シングルを生み出すことはなくなっていた。
NY3部作によって、海外のロック・アルバムにも匹敵するクオリティのサウンドを生み出し、硬派なロック・バンドとしてのポジションを獲得した。ただ、冷静と情熱とを併せ持つ歌詞の世界観は、当時のライト志向のユーザーに訴求するには、ちょっとストイック過ぎた。
最新鋭のレコーディング技術と精鋭スタッフによって、甲斐バンドは孤高のサウンドを獲得し、それは古参ファンやうるさ型の評論家も認めるところだった。ただそんな絶賛も、膨大な経費をリクープするに至らなかった。初動こそ、ベスト10圏内には確実に入ったけど、累計セールスは決して大きなものではなかった。
ライブ活動を縮小してレコーディングされた『Love Minus Zero』には、3枚の既発シングルが収録されている。このシングル・カットはバンド側の意向ではなく、レコーディング予算計上のため、東芝の要請によるものだった、とされている。あまり語られていないけど、決して順風満帆ではなかった台所事情が窺える。
いい意味で、素朴で馴れ親しみやすかった初期のフォーク風歌謡ロック路線は、メンバー内で充分賄えるサイズのサウンドでまとめられていた。ライブでの再現性を前提としたアンサンブルは、ギターとベース、ドラムによるシンプルなパーツの組み合わせによって構成されていた。甲斐の歌とメロディを際立たせるため、複雑なアレンジは必要ない。
ほぼ毎日のようにステージに立ち、バンド演奏を前提とした楽曲制作を行なっていた甲斐よしひろだったけど、キャリアを重ねるにつれ、作風の変化が顕著になってゆく。単純な8ビートやロック・サウンドにはそぐわない、ストリングスやシンセを使う楽曲も多くなり、ベタな歌謡曲メロディは後退してゆく。
ベース長岡和弘の脱退を機に、ユニット形式と移行した甲斐バンドは、徐々に外部ミュージシャンの起用が多くなってゆく。それが頂点に達したのが『Gold』で、ほぼメンバーが参加していないトラックも収録されている。
メンバーの演奏スペックと甲斐の理想のビジョンとの開きは大きくなり、それは人間関係にも大きく影響してゆく。それが頂点に達したこの時期、バンドは解散の危機を迎えている。
とはいえ、メンバーはみな、熱い血潮のたぎる九州男児である。ミーティング時は怒号も飛び交い、時にはつかみ合いになったりもするけど、もともとは友人・知人関係から始まったバンドなので、単なる音楽性の相違だけで解散には至らない。袂を分かつに至った真相は、結局のところ、第三者がとやかく言ってもしょうがない。
甲斐バンド・オリジナルのサウンドを追求するがゆえ、次第に独善的な言動が多くなってゆく甲斐。そして、理解はすれど、スタンド・プレイの多さゆえ辟易するメンバーたち。
どちらが悪いわけではない。単に進むべきベクトルが違ってきただけなのだ。いや、そもそも最初っからスタート地点は違ってた、とでも言うべきか。
デビューから苦楽を共にしてきたこともあって、一蓮托生、いわば運命共同体的なメンタリティもあった甲斐にとって、解散という選択肢はありなかった。ただ、メンバーの好意に甘えたがゆえのサウンド強化、演奏者のプライドを無視した外部ミュージシャンの積極的な導入は、ちょっと独善的すぎた。
日増しにストイックなAOR化してゆく甲斐バンド・サウンドの頂点に達したのが、実質的な最終作『Love Minus Zero』である。ここでひとつの区切りがついたと言ってよい。バンド全員でスタジオに入ることは少なくなり、各パートの個別ベスト・テイクを集結する、スティーリー・ダン方式でレコーディングが進められた。
もはやバンドとしての必然性を感じられないサウンドは、崩壊を予兆するものだった。クオリティは究極を示すものだったけど、バンド・マジックを感じられない『Love Minus Zero』は、評価こそ高かったけど、資本投下に見合うセールスを上げるには至らなかった。
孤高のスタンスでサウンド・クオリティの向上に腐心している最中、時代は確実に動いていた。BOOWYやレベッカら、次世代・さらに次々世代のアーティストがチャートを席巻していた。それに気づいていたのかいなかったのか、ともかくすでに彼らの場所は失われていた。「甲斐バンド」というブランド・ネームが通用していた時代は、もう過ぎ去っていたのだ。
真摯に愚直に、オリジナルを追求していた甲斐バンドは、「過去のビッグ・アーティスト」というポジションに収まっていた。
―もうこれ以上、どこへも動けない。
そう悟った甲斐バンドは、解散を決断する。
『ストレート・ライフ』は、どれも甲斐バンドで演るにはそぐわない、ソロ傾向の強い楽曲中心に構成されている。バンド時代は、合同演奏から誘発されるグルーヴ感がひとつの柱となっていたけど、ここではそういった制約から解き放たれた自由なアプローチが、結果的にサウンドにバラエティ感を添えている。
『Gold』制作時からプリプロ作業が行なわれていたため、当然だけどNY3部作との親和性は高い。実際、この時代はひとくくりにされており、数年前にボックス・セットにまとめられている。
参加ミュージシャンやレコーディング・スタッフもかぶる部分が多いので、バンド時代と地続きと思われがちだけど、実際聴いてみると、バンドとは別の製作意図があちこちで窺える。まぁ当たり前のことだけど。
ここでの甲斐よしひろは、ソングライター以上に、ヴォーカリストとしての側面を強く打ち出している。過剰に歌詞に感情移入せず、フラットな発声でありながら、単調に陥らないヴォーカライズは、もっと評価されてもいい。ロックっぽくしようと変に巻き舌になったり、カタカナ英語やカタカナ日本語でごまかすことなく、きちんと音節や文脈を意識した甲斐のヴォーカルは、実は稀有なものである。過剰な洋楽かぶれやはっぴいえんど史観とはまったく別の流れなので、なかなかフォロワーがあらわれないのも、再評価されずらい一因なのかね。
そういえば、矢沢永吉も巻き舌って使わないよな。2人とも方向性は違うけど、老若男女問わず、誰にでもきちんと伝わる日本語で歌いながらロックを感じさせるのは、案外難しい。あとは民生くらいかな、俺が知る限り。
初期の椎名林檎は思いっきり巻き舌だけど、あれはあれでいい。前にも書いたけど、カワイイは正義だ。
ストレート・ライフ(+3)
posted with amazlet at 19.06.26
甲斐よしひろ
ユニバーサルJ (2003-11-05)
売り上げランキング: 341,831
ユニバーサルJ (2003-11-05)
売り上げランキング: 341,831
1. イエロー・キャブ
度肝を抜かれたサウンド・プロダクション。シンセとシーケンスてんこ盛りなのに、どの音もボトムが太いので、80年代サウンド特有の腰の軽さがまったくない。ちょっとバランスを崩せばとっ散らかった響きになるはずなのに、きちんとまとまっている。聴かせたい音は大きく、そして引っ込ませる音は小さく。それでいて音割れすることもなく、かき消されることもない。
当時、ボブ・クリアマウンテンと双璧をなす一流エンジニアだったJason Corsaro最高のミックスがここにある。甲斐がミックスにこだわった結果が、この曲にぜんぶ込められている、と言っても過言ではない。
なので、当時の最先端だよとこれ見よがしにインサートされたスクラッチ・ビートをとやかく言うのはやめよう。
2. ブルー・シティ
たった今まで知らなかったのだけど、もともとは近藤真彦に提供した楽曲のセルフ・カバー。甲斐ヴァージョンはさんざん聴いてたけど、せっかくなのでマッチさんヴァージョンも聴いてみたのだけど、オケは『Love Minus Zero』テイストのソリッドなロックなのだけど、まぁヴォーカルがちょっと…。
マジで調子悪くなってきたので、再度甲斐ヴァージョンへ。アイドル向けなので歌詞はちょっと甘めだけど、シンセの圧の強いロック・テイストは、マッチとはまた違ったアプローチでこっちの方が好き。
3. 電光石火BABY
「破れたハートを売り物に」をもっとメロディアスにしたシンセ・ビートから始まる、このアルバムのリード・シングル。リリース当時からリック・オケイセックとの関連性が囁かれていたけど、まぁオマージュと受け取れば全然オッケー。ていうか当時はこの程度のリスペクトは当たり前だったし。
ワールドワイド仕様のサウンドを追及していた当時の甲斐だっただけに、世界進出の可能性を模索していたことが窺えるサウンド・プロダクションになっている。質の追求だけでなく、アメリカ市場を視野に入れたコンテンポラリー・サウンドがこのアルバムのテーマであり、それを最も象徴しているのが、この曲。
なので、ちょっとバタ臭い風のPVも日活アクション映画みたいな歌詞も、意気込みのあらわれだった、ということで温かく見守ろう。
4. クール・イブニング
リリース前からみんな知ってた、ご存じ「サウンドストリート」のオープニング・テーマ。ていうかリアルタイム世代しか知らねぇか、まぁいいや。
このアルバムの中では最もシンプルなアンサンブルで、すごく密室的、それでいながら親密さが漂う不思議な曲。淡々と歌いながら、サビやラストでは声を張ってしまうパターンはよくあるけど、メロディの浮遊感もあってか、最後まで淡々としたテンションを保っている。バンド時代にはなかった一面である。
5. レイン
そりゃGodley & Crèmeまんまのアレンジだけど、一歩間違えれば演歌スレスレのベタなメロディをボトムアップさせるには、このサウンドしかなかったわけで。歌謡ロック調のデモ・ヴァージョンは、まぁお蔵入りして納得だな。
「夜ヒット」出演時にこの曲が披露されたのだけど、ギターにストリート・スライダーズの蘭丸が抜擢されて、ファンの間で一時騒然となったことを覚えている。どう辿っても接点のなかった2人がどうして出逢ったのか。ストイックなロッカバラードと蘭丸の小技たっぷりのブルース・フィーリングとの相性は良く、ちょっとした伝説になっている。
当初、話題性を目的にメンバー入りさせたのかと思ってたけど、その後も断続的にこの2人はコラボしているので、相性は良かったのだろう。久しぶりにまたやらないかな。
6. 夜にもつれて
歌詞もコード進行もブルース・タッチだけど、バック・トラックはほぼシンセで構成されている、ある意味チャレンジャーな楽曲。コンボ・スタイルで演ったらもっと泥臭くなっていただろうけど、敢えてモダン・スタイルでやってみたところに、今後の可能性を予見させる。
7. モダン・ラブ
OMDあたりのUKシンセ・ポップに、ピーター・ガブリエルのエキセントリック性を付加したソフト・ファンク。こういうサウンドって流行ったよな。流行りのサウンドを貪欲に取り入れているのが当時の甲斐のコンセプトであり、その後の雰囲気AOR化につながってゆくのだけど、まぁあんまり面白くない。16ビートは合わんよな、甲斐のヴォーカルって。
8. 441 WEST 53rd ST. - エキセントリック・アベニュー
ハードボイルドな世界観とサウンドのボトムアップをテーマとしたのがNY3部作とすれば、厳選されたアウトソーシングによるヴォーカル&インストゥルメントのコンテンポラリー化を目指したのが、『ストレート・ライフ』である。外部の血の積極的な導入は、バンド神話とは一線を画したサウンドの純化につながった。
ドラム:青山純、ベース:伊藤広規、シンセ:難波弘之という参加ミュージシャンからわかるように、これって当時の山下達郎バンド。ドラムの音は思いっきりパワステ仕様でコンプがかけられており、シンセもちょっと時代に寄り添い過ぎてて、もうちょっと何とかならなかったの、と余計なツッコミを入れたくなってしまう。この頃はどんなベテラン・ミュージシャンも迷走していた時代なので、致し方ない部分も多々ある。
サーカス&サーカス2019(初回限定盤)
posted with amazlet at 19.06.26
甲斐バンド
ユニバーサル ミュージック (2019-06-26)
売り上げランキング: 54
ユニバーサル ミュージック (2019-06-26)
売り上げランキング: 54
KAI BAND&YOSHIHIRO KAI NEW YORK BOX(DVD付)
posted with amazlet at 19.06.26
甲斐バンド 甲斐よしひろ 甲斐バンド/甲斐よしひろ 甲斐よしひろ
ユニバーサル ミュージック (2016-06-29)
売り上げランキング: 107,082
ユニバーサル ミュージック (2016-06-29)
売り上げランキング: 107,082