 1974年リリース、引退前最後のMilesバンド、1970年から74年にかけてレコーディングされた未発表曲のコンピレーション。後年になって評価が高まった電化マイルス期のスタジオ録音というのは、1972年の『On the Corner』までであり、それ以降の作品はすべてライブ録音である。そういえばそうだよな、改めて気づいた。
1974年リリース、引退前最後のMilesバンド、1970年から74年にかけてレコーディングされた未発表曲のコンピレーション。後年になって評価が高まった電化マイルス期のスタジオ録音というのは、1972年の『On the Corner』までであり、それ以降の作品はすべてライブ録音である。そういえばそうだよな、改めて気づいた。 多分、この時期のMilesはアルコールとドラッグによる慢性的な体調不良を抱えていたため、支払いが遅く時間の取られるスタジオ作業より、チャチャっと短時間で日銭の入るライブに重点を置いていたんじゃないかと思われる。野放図な当時の生活を維持するため、コロンビアのバンスもバカにならない金額になっていただろうし。
とはいえ、まったくスタジオに入らなかったわけではない。この時期のセッションを収録したコンピレーションは、以前レビューした『Big Fun』もあるし、裏も表も含めて発掘された音源は、そこそこある。
この時期のMilesセッションは、「長時間テープを回しっぱなしにして、後でスタジオ編集」というスタイルが確立していたため、マテリアルだけは膨大にあるのだ。それがまとまった形にならなかっただけであって。
実際、収録されているのは、そのとっ散らかった72年から74年のセッションが中心となっており、70年のものは1曲だけ。その1曲が「Honky Tonk」なのだけど、メンツがまぁ豪華。John McLaughlin、Keith Jarrett、Herbie Hancockと、当時でも十分重量級だった面々が名を連ねており、これだけ聴きたくて買った人も相当いたんじゃないかと思われる。
リリース当時は、酷評か黙殺かご乱心扱いだった『On the Corner』の布陣では、プロモーション的にちょっと引きが弱いので、無理やり突っ込んだんだろうな。Miles もコロンビアも、そのくらいは考えていそうだもの。
前述したように、この時期のMilesのレコーディングは、1曲通しで演奏したテイクが完パケとなることが、ほぼなかった。『On the Corner』も『Jack Johnson』も『Bitches Brew』も、プロデューサーTeo Macero による神編集が施されて、どうにか商品として出荷できる形に仕上げられている。
「テーマとアドリブ・パートの順繰りをざっくり決めて、チャチャっと何テイクかセッション、デキの良いモノを本テイクとする」、そんなジャズ・レコーディングのセオリーとは明らかに違う手法を確立したのがMilesであり、彼が生み出した功罪のひとつである。プレスティッジ時代に敢行した、超スパルタのマラソン・セッションを経て、既存の手法ではジャズの枠を超えられないことを悟ったMilesがたどり着いたのが、レコーディング設備をも楽器のひとつとして捉えるメソッドだった。当時のポピュラー・シーン全般においてもあまり見られなかった、偏執狂的なテープ編集やカットアップは、電化に移行しつつあったMilesとの相性が格別良かったと言える。
メロディやテーマもコードも埋もれてしまう『On the Corner』で確立されたリズムの洪水は、セッションを重ねるごとにインフレ化し、次第にポリリズミカルなビートが主旋律となる。メインだったはずのトランペットの音色も、電化によって変調し増幅され、音の洪水に埋没してゆく。制御不能となったリズムに身を委ね、自ら構成パーツのひとつとなることを望むかのように。
『On the Corner』までは、バンマスとしての役割を辛うじて果たしてはいたけど、これ以降のMilesは、自ら生み出したリズムの怪物に振り回され、侵食されてゆく過程を赤裸々に描いたと言ってもよい。
「混沌をコントロールする」というのも妙な話だけれど、『On the Corner』期のセッションでは、そのヒントが得られたはずだった。JBやSlyによって発明されたリズムからインスパイアされ、メンバーにもファンクのレコードを繰り返し聴かせた、というエピソードが残っているように、新たな方向性を見出して邁進するMilesの昂揚感が刻まれている。
「じゃあ、さらにリズムのインフレを人為的に起こしたら、一体どうなるのか?」というフィールド・ワークが、いわばこの時期のライブであり、スタジオ・セッションである。エンドレスに続くリズム・アンサンブルから誘発されるグルーヴ感に対し、無調のメロディをカウンターとしてぶつける、というのが、当時のMilesのビジョンだったんじゃないかと思われる。
大勢による複合リズムに対抗するわけだから、単純に音がデカい、またはインパクトの強い音色でなければならない。なので、Milesがエフェクターを多用するようになったのも腑に落ちる。もはや「'Round About Midnight」のような繊細なプレイでは、太刀打ちできないのだ。
「俺のソロの時だけ、一旦ブレイクしろ」と命令も無意味で、それをやっちゃうと、サウンドのコンセプトがブレる。リーダーの一声で制御できるリズムなんて、Milesは求めていないのだ。
強いアタック音を追求した結果、ギターのウェイトが大きくなるのも、これまた自然の流れである。ただ、Milesが求めるギター・サウンドは、一般的なプレイ・スタイルではなかった。かつてはあれだけお気に入りだったMcLaughlinの音でさえ、リズムの洪水の中では大人しすぎた。
カッティングなんて、気の利いたものではない。弦を引っ掻き叩く、まるで古代の祝祭のごとく、暴力的な音の塊、そして礫。流麗さや優雅さとはまるで対極の、感情のうねりと咆哮-。
そんな流れの中では、どうしても分が悪くなるのが、ピアノを筆頭とした鍵盤系。アンプやエフェクトをかませてブーストできるドラムやギターの前では、エレピやオルガンは立場が薄くなりがちである。
もう少しパワーのあるシンセだって、当時はモノフォニック中心で、スペック的には今とは段違い、ガラケーの着メロ程度のものだったため、あまりに分が悪すぎる。メロディ・パートの表現力において、ピアノは圧倒的な優位性を有してはいるけど、でも当時のMilesが求めていたのは、そういうものじゃなかったわけで。
リズム志向とは別枠で、電化マイルスが並行して模索していたのが、Stockhausenにインスパイアされた現代音楽の方向性。メロディ楽器というより、一種の音源モジュールとしてオルガンを使用、自ら演奏しているのが、収録曲「Rated X」。ゾロアスターの教会音楽や二流ホラー映画のサントラとも形容できる、既存ジャズの範疇ではくくれない実験的な作品である。
ただこういった使い方だと、いわゆるちゃんとしたピアニスト、KeithやHerbie、またChick Coreaだって使いづらい。言っちゃえば、単なるロング・トーンのコード弾きだし、いくらMilesの指示とはいえ、やりたがらないわな。
「ジャズに名曲なし、名演あるのみ」という言葉があるように、ジャズの歴史は主に、プレイヤビリティ主導で形作られていった。すごく乱暴に言っちゃえば、オリジナル曲もスタンダード・ナンバーも、あくまでセッション進行の目安に過ぎず、プレイヤーのオリジナルな解釈やテクニック、またはアンサンブルが重視される、そんなジャンルである。
スウィングの時代なら、口ずさみやすいメロディや、ダンスに適したノリ重視のサウンドで充分だったけど、モード・ジャズ辺りから芸術性が求められるようになる。「ミュージシャン」が「アーティスト」と呼ばれるようになり、単純なビートや旋律は、アップ・トゥ・デイトな音楽と見なされなくなっていった。
時代を追うに従って、ジャズの芸術性は次第に高まっていった。そんな中でも先陣を切っていたのがMilesである。若手の積極的な起用によって、バッサバッサと道なき道を開拓していった。

ただ、ジャズという枠組みの中だけでは、新規開拓も限界がある。60年代に入ったあたりから、モダン・ジャズの伸びしろは頭打ちを迎えることとなる。
プレイヤーの表現力や独創的な解釈に多くを頼っていたモダン・ジャズは、次第にテクニック重視と様式美に支配されるようになる。ロックやポップスが台頭する中、冗長なインタープレイと腕自慢がメインとなってしまったジャズは、すでに伝統芸能の領域に片足を突っ込んでいた。
ヒップな存在であったはずのMilesが、そんなジャズの窮状に明確な危機感を感じたのが、ファンクの誕生だった。「-今までやってきた音楽では太刀打ちできない」、そう悟ったのだろう。
いわば電化マイルスとは、既存ジャズへの自己否定とも言える。好き嫌いは別として、モード以降のジャズを作ったのがMilesであることは明確だし。
これまでのジャズの人脈とはちょっと外れたミュージシャンを集め、冗長なアドリブ・パートを廃し、ひたすら反復リズムを刻むプレイに専念させる。そこにスター・プレイヤーや名演は必要ない。集団演奏によって誘発される、邪悪でデモーニッシュなグルーヴ。それが電化マイルスの基本ビジョンだったと言える。
これまでジャズのフィールドにはなかった現代音楽やファンク、エスニックの要素を取り入れた、複合的なごった煮のリズムとビートの無限ループ。その音の洪水と同化しつつ、クールな頭脳を保ちながら最適なソロを挿し込む作業。その成果のひとつ、電化マイルスの第一の到達点が『On the Corner』だった。
じゃあ、その次は?
Milesが隙間なく組み上げたサウンドとリズムの壁は、盤石なものだった。なので、あとはもう壊してゆくしかない。
ただ、完璧に壊すためには、完璧に創り上げなければならない。もっとリズムを・もっと激しく。リズムのインフレの始まりである。
こうなっちゃうと、もう何が何だか。どこが到達点なのかわからなくなる。
-完璧なサウンドなんて、一体誰が決める?
そりゃもちろんMilesだけど、そのジャッジはとても曖昧だ。ただでさえ、酒やドラッグで精神も脳もやられているため、朝令暮改が日常茶飯事になる。昨日言ったこと?ありゃナシだ。もう一回。
未編集のまま放り出された録音テープが溜まりに溜まり、いつものTeoに丸投げするけど、もはや彼の手にも追えない。だって、あまりに脈絡が無さすぎるんだもの。どう繋いだり引き伸ばしたりしても、ひとつにまとめるのは無理ゲー過ぎ。
なので、『On the Corner』以降の作品が、このようなコンピレーションかライブ編集モノばかりなのは、致し方ない面もある。逆に言えば『Get Up With It』、無理にコンセプチュアルにまとめることを放棄し、多彩な実験を無造作に詰め合わせたことによって、当時のMilesの苦悩ぶりが生々しく表現されている、といった見方もできる。
誰もMilesに「ハイ、それまでよ」とは言えなかった。自ら崩壊の過程を線引きし、その線をなぞるように坂道を転げ落ち、最期のアガ・パンにおいて、志半ばで前のめりにぶっ倒れた。
後ろ向きには倒れなかった。これが重要なところだ。試験に出るよ。
1. He Loved Him Madly
1974年、ニューヨークで行われたセッション。レコーディング中、Duke Ellingtonの訃報の知らせを聞き、追悼の意を込めてプレイされた。そんな事情なので、ミステリアスな沼の底のような、地を這うようなサウンド。呪術的なMtumeのパーカッションと交差するように、ジャズと呼ぶにはオルタナティヴ過ぎなPete Coseyら3本のギター。ジャズとして受け止めるのではなく、かなりイっちゃったプログレとして捉えことも可能。あんまり抑揚のないプレイだけど、Pink Floydがジャズをやったらこんな感じ、と思えば、案外スッと入ってこれるんじゃないかと思われる。
ちなみにMiles、前半はほぼオルガンに専念、後半になって浮遊感に満ちたワウワウ・ソロを披露している。
2. Maiysha
一昨年話題となった、Robert Glasper & Erykah Baduコラボ曲の元ネタ。1.とほぼ同時期に行われた、カリプソ風味のセッション。またオルガンを弾いてるMiles。この頃、マイブームだったんだろうな。
カバーだオリジナルだと区別する気はないけど、この曲においては、Glasperのアイディア勝ち。Erykah Baduもこういったコラボにお呼びがかかることが多いけど、シンガーに徹したことによって、変なエゴが抑えられて程よい感触。
Milesが土台を作ってGlasperがコーディネート、彼女によって完成された、と言ってもいいくらい、渾身のクオリティ。漆黒の重さを求めるならオリジナルだけど、ポップな歌モノを求めるなら断然こっち。多分Miles、Betty Davisにこんな風に歌って欲しかったんじゃないか、と勝手に妄想。
3. Honky Tonk
ジャズ・ミュージシャンがロックをやってみたら、こうなっちゃました的な、McLaughlinのためのトラック。一瞬だけスタメンだったAirto Moreiraのパーカッションが泥臭い風味で、単調になりがちなサウンドにアクセントをつけている。まだ電化の発展途上だった70年のレコーディングなので、Milesもオーソドックスなプレイ。彼が思うところの「ロック」はブルースに大きく寄っており、ジミヘンの出すサウンドに傾倒していたことが窺える。
そんな感じなので、KeithとHerbieの影はとてつもなく薄い。どこにいる?
4. Rated X
「人力ドラムン・ベース」と俺が勝手に評している、キャリアきっての問題作。要はそういうことなんだよな。ジャズというジャンルからとことん離れようとすると、ここまで行き着いちゃうってことで。テクノと教会音楽が正面衝突して癒着してしまったような、唯一無二の音楽。無限リズムの中を徘徊し、気の赴くままオルガンをプレイするMiles。本職なら選びそうもないコードやフレーズを放り込みまくっている。
5. Calypso Frelimo
カリプソとネーミングされてるため、享楽的なトラックと思ってしまうけど、実際に出てくる音は重量級のファンク。『On the Corner』リリース後間もなくのセッションのため、余韻がハンパない。なので、ワウワウを効かせまくったMilesのプレイも至極真っ当。このタッチを深く掘り下げる途もあったはずなのだけど、サウンドの追及の末、ペットの音色さえ余計に思うようになってしまう。
6. Red China Blues
1972年録音、珍しい名前でCornell Dupree (G)が参加、ドロドロのブルース・ナンバー。ハーモニカはうなってるし、ホーン・セクションもR&B風。「へぇ、よくできまんなぁ」と絶賛したいところだけど、誰もMilesにオーソドックスなブルースは求めていないのだった。ギターで弾くフレーズをトランペットで鳴らしているあたり、こういった方向性も模索していたんだろうけど、まぁそんなに面白くはない。自分でもそう思って、ボツにしちゃったんだろうな。
7. Mtume
レコードで言うD面は人名シリーズ。タイトル通り、パーカッションをフィーチャーしたアフロチックなナンバー。もはやまともなソロ・パートはなく、引っかかるリフを刻むギター、そしてパーカッションの連打連打連打。
で、Milesは?存在感は薄いけど、最後の3分間、ビートを切り裂くようなオルガンの悲鳴。さすがフレーズの入れどころがわかってらっしゃる。
8. Billy Preston
あのBilly Preston。Beatles 『Let it Be』で一躍脚光を浴びた、あのBilly Prestonである。ソウル好きの人なら、「Syreetaとコラボした人」と思ってるかもしれない。でもこのセッションBlly Prestonは参加してないという不思議。どこいった?Bille Preston。
曲自体はミドル・テンポの軽めのファンク。このアルバムの中では比較的リズムも安定しており、Milesも真っ当なプレイ。あ、こんな言い方じゃダメだな、電化が真っ当じゃないみたいだし。



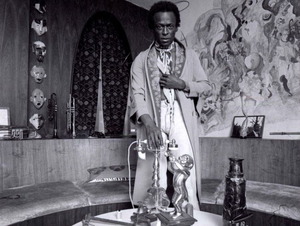

















![モ'・ベター・ブルース [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51QShDSxv5L._SL160_.jpg)

